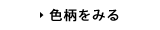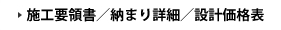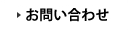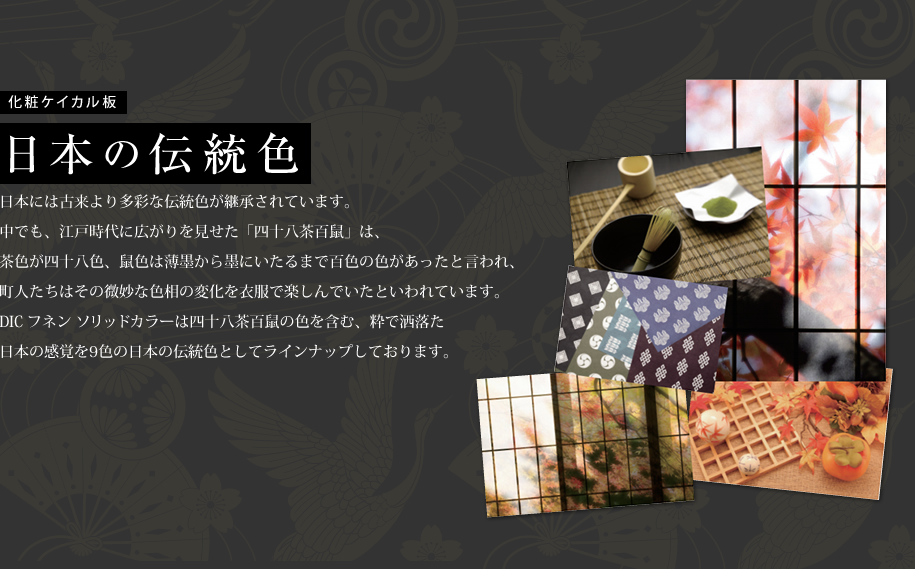
-

D-053 威光茶
(いこうちゃ)茶(ブラウン)という名の範囲からはずれてこのように緑がかった色を茶と呼ぶのは、日本では茶道のお茶の色からきているのであろう。柳茶、鶸茶(ひわちゃ)などと呼ばれる色と同類の色である。
-

D-054 納戸鼠
(なんどねず)錆納戸より更にくすんで、わずかに納戸かかった鼠色をいう。藍色、納戸色、錆納戸、納戸鼠の順に彩度が低い色になる。
-

D-067 藍鼠
(あいねず)鼠色に藍色がかった彩度に低い色をいう。鼠(ねず)も比較的近世にもちいられるようになった形容で、古い伝統色名では減(けし)の形容後が用いられていた。減藍(けしあい)ともいう。
-

D-080 灰白
(はいじろ)灰みがかった白をいう。霜のような白のフロスティホワイト(frosty white)、真珠のような白のパールホワイト(pearl white)の名がある。
-

D-081 銀鼠
(ぎんねず)銀は独特の銀光沢をもっているが、色名としての銀鼠は光沢は別にして、銀は明るい色の形容であるから、明るいグレイをいう。英名ではシルバーグレイ(silvergray)である。
-

PD-091 柿色
(かきいろ)照柿の実のような色をいう。歌舞伎の世界で言われる柿色は、この色ではなく、団十郎茶と言われている茶がかった色である。
-

PD-094 露草色
(つゆくさいろ)露草の花に見る色、この花をすった汁を青花といい、染色の下絵をかくのに用いた。万葉人はこれを着草(つきくさ)と呼び、これで衣を染めたこともあった。月草の名はそこから生まれた。この色は花色ともいう。
-

PD-113 支子色
(くちなしいろ)支子の花は白くて香りが強いが、その実から採る色素は黄色で、これで染めた色をいう。黄支子とも言われる。くちなしだから「言わぬ色」ともいった。
-

PD-123 豌豆緑
(ピーグリーン)ピーグリーンは英語圏では慣用されている色名で、豌豆のさやの中に並ぶかわいい豆つぶの色からきた名である。豌豆緑はその訳名である。